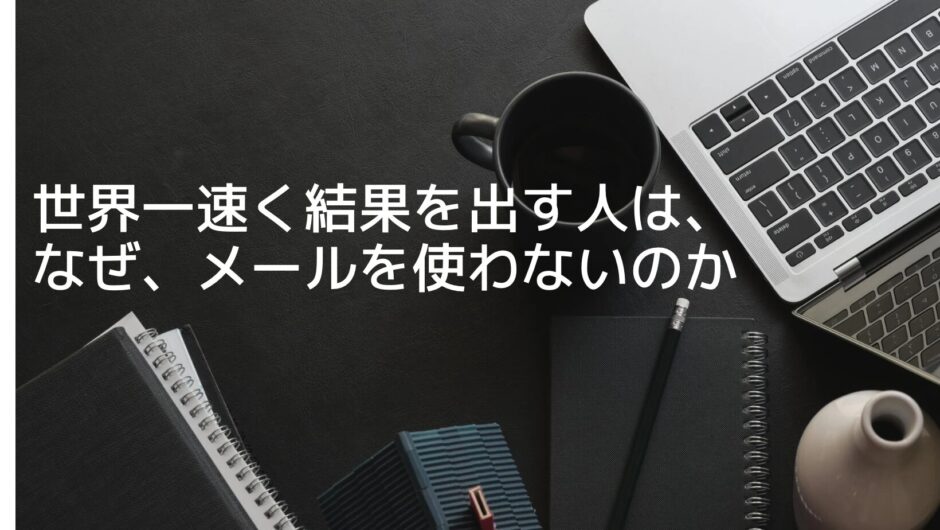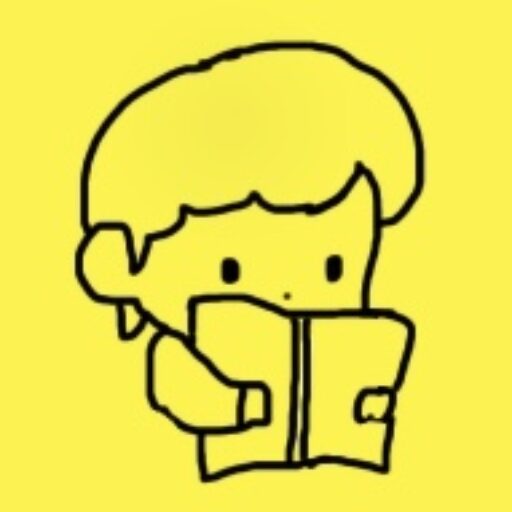
「世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか 」を読みました

グーグルの従業員1人あたりの生産性は日本企業と比べると4倍だとか。
どうしてそんなに生産性が高いのかなあ、気になるよ
タイトル 世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか グーグルの個人・チームで成果を上げる方法
著者 ピョートル・フェリークス・グジバチ
出版社 SBクリエイティブ
発売日 2017/1/27
ページ数 227
Kindle Unlimited 対象外
Audible 対象
この本を読む動機は、時間に追われている状況をどうにか改善したいと考えたからです。
今回はAmazonのオーディオブック、【オーディブル】で聞く読書をしました。
時間に追われているがゆえ、時間を有効活用しようと思いまして。
家事をしつつ(主に皿洗いと、料理中)読書を楽しみました。
Googleの仕事術、核心をついていて会社、家庭、サークルなど、どんなコミュニティでも活かせると思います。
著者は金融機関グループのモルガン・スタンレーを経て、Googleにて人材開発、そして独立をされています。
Googleの日本支社での勤務にて、部下との関わりやチームでの成果の挙げ方など、学べるところが多かったです。
アイデア出しはユニークな職場環境とチームの総合力
Googleの職場を見たことがありますか?
かなりユニークなデザインのオフィスで驚くと思います。
ビリヤードがあったり、サッカーやバスケができたり。
仮眠できるポッドまである。
日本支社にも独自の部屋があるそうで、ここ本当に会社なのかな?と首をかしげてしまいそうですが、会社に行くのが楽しくなりそうです。
しかし、たくさんの誘惑がある中で仕事に集中できるのか、と思う人も少なくないはず。
ところがこれは全て効率を良くするために必要とのことだそう。
アイデアを出すには自分のデスクにいるより、作業スペースを移動してひらめきを得たり体を動かたり休息を取ることが、良い仕事に繋がるのかなと思いました。
読んでいて感じたのはアイデア、創造の連続で仕事をされているんだなと。
無限キャベツ、無限列車、無限アイデア、そうあの「無限」。
羨ましさを感じたのは、社員がみな信頼し合い風通しの良いところです。
ミーティングは部署ごとに行うのではなく、他部署のあの人にも参加してもらおう、とか。
ちょっといい?の声かけだけですぐミーティングが始まるところとか。
フットワークが軽いし、時間に対する姿勢が違います。
悩んで時間をかけたら良いアイデアが浮かぶといったら、そうでもないですもんね。
この本を読んでいて、この考え方知ってるなと思ったことが2点。
一つは林修先生。「いつやるか、今でしょ!」の林先生です。
そしてもう一つは「文殊の知恵」
3人集まれば良い知恵がでるという、ことわざです。
Googleは『今』というこの瞬間と『チームの総合力』を最大限に活用して、新しいモノを生み出しているのだと思いました。
目標は高く設定し自分を進化させる
書籍の中で「10X(テンエックス)」という言葉が出てきます。
10倍で物事を考えるということだそうです。
2倍速という言葉はよく聞きますが、10倍はなかなか聞きませんね。
余裕で達成できる目標より、ギリギリ達成できないかもという目標の方が人を成長させます。
達成するために考えて行動します。
闇雲に動くより効率的で生産性も高くなる。
読んでいて分かったのですが、Googleは個人を成長させるような後押しをしてくれる制度や、人間関係が構築されていました。
驚くほどの速さで世界が変化してるからこそ、人間も常に考えて突飛した発想で変化していかなくてはいけないのですね。
また、世界やユーザーもそれを求めている。
企業として世界をより良くしていこうという姿勢が伝わってきました。
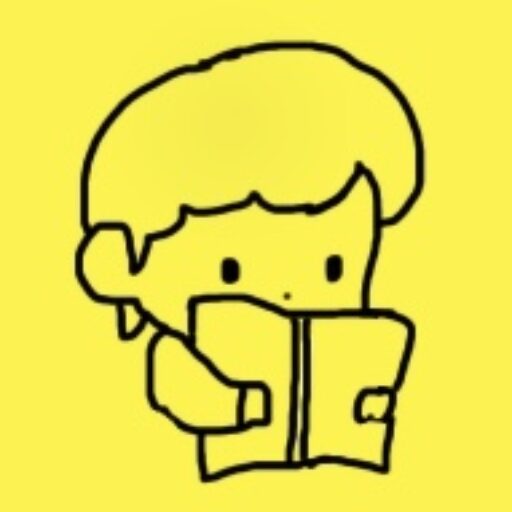
限界突破というより、今のやり方とは違う次元でやるということだね
さいごに
タイトルの「なぜ、メールを使わないのか」というのは、メールだとお互いに微妙なズレが生じて目指すゴールが違ってくるし、修正に時間を要する。
会って話した方がニュアンスも伝わりやすく、メールを往復させるより時間を節約できて結果に早く結びつくよ、ということなのかと思います。
始めにも書きましたが、今回はAmazonの【オーディブル】にて耳で聴いて読書をしました。
小説では味がなくなるやり方ですが、1.2倍速、1.5倍速にして2回聴きました。
(繰り返し聴くことで記憶に定着します、聴く方が早く読み返せて時短)
1回目は1.2倍速で全体をざっと理解(約4時間15分)
2回目は1.5倍速にして、気になるところをクリップしながらより理解を深めました(約3時間)
クリップとは蛍光マーカーのような役割をします。
クリップしたところだけ後から聴くことができ、自分に必要な箇所だけ繰り返し確認できます。
初の【オーディブル】でしたが、自分が進化したように感じます。
紙の本から電子書籍へ、電子書籍から【オーディブル】へ。
著者のピョートルさんもこうおっしゃっていました。
「変わらないこともまたリスクなのです」と。
流れの早い時代だからこそ、自分という軸を失わず変化ウェルカムで活動的でいたいと思います。